日本の大学、大学院留学情報JPSS > ニュース/留学に役立つ情報 > 日本留学案内 > 外国人のための危機管理講座 > 「どこへ避難すればいいの?」
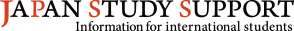

地震などの災害が発生し、家が危なくなった場合は外へ避難します。さて、どこへ行けばいいでしょうか。行政上、災害の状況によって次のような順序で避難することになっています。
(1) 一時避難場所(一時集合場所)
まずは自宅の近所にある公園や学校の校庭などの広いスペースに一時的に避難し、しばらく様子を見る。一時避難場所は地域の町内会などで決められていることがある。
(2) 広域避難場所
一時避難場所が危なかったり、一時避難場所へは危険で行かれない場合に、より大きな公園や広場に集まって火事がおさまるのを待つ。広域避難場所は市区町村によって指定されている。
(3) 避難所
自宅が倒壊などの被害にあって生活できないような場合に、しばらく生活する場所。通常、地域の小学校や中学校などが市区町村によって避難所として指定されている。
避難の順序について、「東京都防災ホームページ」内にわかりやすく図で示してあります。
では、自分が住んでいる地域の避難場所、避難所はどこにあるのでしょうか。
東京都では「東京都防災マップ」を作っていて、市区町村ごとに避難場所、避難所がわかるようになっています。
| その他の地域のサイト | |
|---|---|
| 札幌市 | 「どこへ避難するの?」 |
| 大阪市 | 「各区の防災マップ」 |
| 神戸市 | 「災害時の避難所」 |
| 福岡市 | 「福岡市防災マップ」 |
また、インターネットで「市区町村名 避難場所」で検索すると各自治体が作成しているサイトにて避難場所の一覧が出てきますので、自分の住んでいる地区の避難場所、避難所を必ずチェックしておきましょう。
各市区町村が作成している防災ホームページやガイドブックでは、避難場所や避難所を示すのに「○○町○丁目○番地~○番地の皆さんは○○小学校」というように書かれていることが多く、地区名や学校名、公園名とその地理が分かっていないと理解できません。また、地図も示されていますが、外国に住んでいる場合、地図を見ただけではなかなか実際の街の様子(遠いのか近いのか、通る道は広いか狭いか、その避難場所はどんな土地なのか、など)が想像できないと思います。
そこで、本当の災害が起きる前に自分が住んでいる地域の避難場所、避難所まで実際に歩いて行ってみることをおすすめします。実際に歩けば、こんなに遠いのか、ここは横断歩道がないから危ないな、この歩道橋は災害時は危なそうだから渡らない方がいいな、などと体感できると思います。実際の避難時にあわてないためにも必ず事前に下見をしておきましょう。
さらに、周辺の地区名、学校名、公園名とその位置関係を普段からよく把握しておきましょう。災害時に警察や消防から「○○町の皆さんは○○公園に避難してください!」という放送があったときに、その公園がどこにあるのか分からなかったらどうしようもありません。
以前にも書きましたが、家が無事で周りに火災の危険がなければ避難する必要はありません。避難が必要な時は、例えば以下のような場合です。
また、避難する際は次のことに気をつけてください。