日本の大学、大学院留学情報JPSS > ニュース/留学に役立つ情報 > 日本留学案内 > 留学生生活案内 > 宿舎を探す
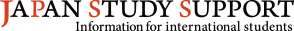

東京などの大都市圏での宿泊は日本人にとってもとても問題です。日本人が部屋を探す時も、電車の乗り降りを繰り返しながら、足を棒のようにして、沿線を回ります。また、外国人には、部屋を貸したがらない大家や、不動産屋もありますが、勇気を奮い起こし、探してみましょう。
(1)在学先の学生寮
留学生向けに寮などの宿舎を用意している学校もあれば、民間宿舎の紹介だけをする学校など、さまざまです。来日して宿舎に困っている人は、まず在学先の担当窓口にたずねて下さい。
(2)留学生寮
国・東京都あるいは民間団体が経営する留学生寮も少数ながらあります。設備も良く費用も安いのですが収容数や入寮資格が限定されています。学校の担当窓口で紹介されることもあります。
(3)公営住宅
都道府県や市区で提供している公営住宅には、1年以上日本に在留し、同居親族がいる地域在住の外国人が申し込むことができる場合があります。ただし交通の便のよい公営住宅は希望者が多く、なかなか入居できません。問い合わせは各都道府県等の住宅局管理部募集課へ。
(4)日本企業の社員寮
公益財団法人留学生支援企業協力推進協会(中央区日本橋)では企業の協力を得て、企業の社員寮への留学生の受け入れを進めています。受け入れは大学を通して行われます。
(5)民間の賃貸宿舎
■アパート:木造建築またはプレハブ建築で、通常は2階建ての集合住宅。台所・トイレは共同または専用、風呂はない所も多い。
■マンション:鉄筋コンクリート造りで、通常は3階建て以上の集合住宅。部屋のほかに台所・トイレ・風呂がある。高い階の部屋ほど家賃も高い。
■一戸建て:独立した家屋。一階だけの平屋か2階建てが普通で、小さな庭もついている。もちろん台所・バス・トイレ付き。
■貸間:家主と同じ建物の一部を借りる形式。家主と同じ玄関を使い、台所・風呂・トイレを共同で使う、部屋だけ借りるなど、条件はさまざま。
■ホームステイ:日本人の受け入れ家庭に、家族の一員として滞在する形式。日本文化や習慣を知るため希望者は多いが、受け入れ家庭は極度に少ない。
(1)日本語の日常会話ができないと民間アパートは借りにくい。
民間アパートを借りるためには、家主(大家さん)と話し合わなければなりません。日本では地域ごとに異なる生活上の決まりがあり、こうした生活上の注意事項を日本語で話し合えない人には大家さんはなかなか部屋を貸したがらないのです。
(2)東京、大阪など大都市圏では"通学時間1時間"は普通のこと
学校まで歩いていきたい、自転車で通える距離に住みたいと思っている人もいるでしょうが、特に学校がビジネス地区・商業地区にある場合は不可能と思った方がいいでしょう。日本人学生や市民は、住宅事情と自分の経済状況とを考え、1時間以上の遠距離通学・通勤をしています。 また複雑な鉄道網・地下鉄を上手に利用することも大切です。「乗り換えはイヤ」という発想では都市部で部屋を探すことは難しくなります。複雑そうに見える都市内交通ネットワークにも若いあなたは、すぐ慣れるはずです。
(3)支払える家賃の上限を決める
まず毎月の家賃にいくら支払えるかを正確に考えておいて下さい。アパートの家賃は、地域・建築年数・設備・広さによって異なります。また民間宿舎の賃貸契約は、家賃の支払期限について非常に厳しく、「少し遅れても許してもらえるのでは?」と言う考え方は決して通用しません。
(4)部屋の呼び方を知る
1部屋+台所のアパートを「1K」と呼びます。(マンションの場合は「ワンルームマンション」と呼びます。)、2部屋+食卓の置ける台所のあるアパートを「2DK(2室+Dining Kitchen)」、台所のある部屋がさらに広ければ「2LDK(2室+Living Dining Kitchen)」と呼びます。
民間の宿舎を借りるとき、月額の家賃相場(通常価格)を知っておかないと不便です。一般に都心部に近いほど高く、都心部からの距離が遠ければ遠いほど、安くなります。また、駅からの距離、建築年数、周りの環境、日当たり、住宅地としての人気によっても異なります。
(1)在籍する大学・学校の事務室で紹介を受ける
日本の大学や専修学校、日本語学校では、在籍する学生に、学校の周辺にある学生向きの民間宿舎を紹介しています。事務室でたずねてみて下さい。
(2)不動産屋で部屋を探す
不動産屋は、アパート、マンションなどを斡旋する業者です。駅の周辺に多く「◯◯不動産」「××ホーム」などの看板が出ています。入口のガラス戸や窓などには、アパートの賃貸条件を書き込んだ紙をたくさん貼っていますので、すぐ目につきます。 →『不動産屋に斡旋を依頼する場合の基礎知識』を必ず参照してください。
(3)インターネットで部屋を探す
住宅・不動産の情報サイト「SUUMO(スーモ)」
https://suumo.jp/
■気に入った部屋があったら、すぐに電話してみる
条件の合う部屋があったら、すぐに電話してみましょう。その部屋がふさがっている場合でも、すぐに電話を切らずに「同じような条件の部屋はないですか?」と聞いてみて下さい。日本人も、気に入った部屋を探すために、根気よく数多くの不動産屋さんをまわって部屋探しをしているのです。
(1)普通は、アパートなどの賃貸宿舎には家具が付かない。
たとえば台所も、流し台は付いていますが調理用ガス台は付いていない例が多く、照明器具、敷物、カーテンなども自分で用意することになります。
(2)敷金、礼金、仲介手数料など
契約するときに、敷金・礼金・仲介手数料・家賃等、合計で家賃の5~6ヶ月分程度のお金を用意しなければなりません。
(3)保証人
契約するときに、日本人の連帯保証人を求められます。これは日本人が宿舎を借りる場合にも同じです。
(4)日本語の上手な人といっしょに行く
不動産屋で部屋を探すときには、日本人の友人や身元保証人、あるいは日本語の上手な先輩といっしょに行き交渉を手伝ってもらうと、よい結果を得られます
(5)不動産屋での紹介の手順
■ 自分の希望条件を伝え、気に入った物件があれば、現地に案内してもらって実際に部屋を見ます。
■ 見て気に入らなければ、断ってかまいません。案内料は無料です。気に入ったが1~2日考えたい、友達に相談したい、という場合には、そのことを不動産屋に伝えて下さい。
■ 「手付け金を支払って欲しい」と言われることもあります。手付け金を支払えばその宿舎を借りる優先権を持つことになります。そこに入居すれば、敷金・礼金の一部になりますが、入居しない場合は返却されないことが多いので、よく確認の上支払うようにして下さい。
(6)不動産屋の仲介で部屋を探すときの注意点
■ 1ヵ月の家賃はいくらか。他に管理費や共益費があるかどうか。
■ 交通の便、駅からの距離、近所に商店街があるか、風呂屋(銭湯)への距離など。
■ 日当たり具合などをよく観察して決めて下さい。
■ どんな暖房器具を使えるかも確認しておいて下さい。火災防止のために、ガス・石油ストーブの使用を禁止しているアパートもあります。
■ 隣近所の騒音がひどい場所もありますので、住んでいる人の意見を聞くことができれば、いっそう参考になるでしょう。
■ 賃貸契約書には、重要事項がすべて記入されている。アパートやマンションなどの民間宿舎を借りるときには、借りたい人と家主のあいだで賃貸契約を結びます。
■ 普通は2~3通の同じ内容の賃貸契約書を作り、家主・借りる人・連帯保証人が住所・氏名を書き、捺印して一通ずつ保管します。
■ 賃貸契約書の書式は、たいてい家主側が用意します。また、不動産屋が家主の代理人になる場合もあります。
■ 契約書は、契約期間、契約内容、敷金の預かり金額などの証拠となるものですから、契約を解約するまで大切に保管して下さい。
(1) 契約に必要な言葉と知識
■家賃: 1カ月の部屋代のこと。普通は月末までに、翌月分の家賃を前払いする。不動産会社管理のマンションなどでは、約束の期日から一週間以上遅れると、10%程度の延滞金がかかる場合もある。
■敷金(保証金):家賃の滞納や部屋の損傷に対する保証金として家主に預けるお金で、家賃の1~2カ月分くらい。部屋を明け渡す(他の場所へ転居する)時に、清掃代・修理代を差し引いて残りがあれば返金される。
■礼金(権利金):家主に支払う一時金で、家賃の1~2カ月分くらい。敷金と違い、部屋を明け渡すときにも返金されない。
■共益費(管理費):階段・通路・共同トイレなどの共同部分の電気料・水道料・清掃費や管理維持に必要な一カ月間の費用のこと。
■仲介手数料:不動産屋に支払う手数料。家賃の一カ月分が普通。
(2) 内容を理解してから契約をしよう
どこの国でも法律用語は理解しにくいものです。しかし契約書は、署名・捺印すれば法律的に有効になりますから、内容をよく理解してから署名・捺印して下さい。分からない点は学校の留学生担当者か日本の事情に詳しい先輩に確認して下さい。
(3) 契約の有効期限
賃貸契約期間はたいてい2年です。契約書に記入されている契約の更新の時期や費用についても、よく読んでおいて下さい。
(4) 家主に無断で家族や友人を同居させたり、他人に貸してはいけない
■日本の民間宿舎では、契約した人以外の人は住むことができません。これは諸外国と異なる日本の社会習慣の一つです。もし二人で住みたい場合は、最初からそのことを不動産屋さん(大家さん)に言っておく必要があります。
■親類の人や友人を宿泊させる時には、たとえ短い期間でも必ず事前に大家さんに事情を話して了解をとって下さい。外国人をめぐる宿舎トラブルで、最も多いのが、この貸した人以外の人が住んでいるというケースです。
(5) 家主に無断で部屋を改造してはいけない
家主に断らずに、借りた部屋の内部を改造することはできません。不便な点を変えたいときには必ず家主と相談して下さい。
(6) 部屋の明け渡しにも決まりがある
■引越しをする時の通告期限も契約書で決められています。普通は1カ月前までに家主に伝えることになっています。急に通告した場合、住んでいなくても1カ月分の家賃を支払わなければなりません。
■部屋は入居時と同じ状態にして家主に明け渡すのが原則です。不要品は決められた方法で捨てて下さい。不要品やごみを置いたままで引越しすると、家主に迷惑をかけることになります。また、電気・ガス・水道などの光熱費や電話料の清算も忘れないようにして下さい。
不動産屋でアパートやマンションを紹介してもらう時には、ほとんどの場合、「日本人の連帯保証人が必要です」といわれるでしょう。そこで連帯保証人とは何かを説明しておきましょう。
■連帯保証人の条件
連帯保証人は、「独立の生計を営む成人」つまり家計を支える収入のある人でないと、引き受けることができません。
■賃貸契約の連帯保証人は、債務保証責任を負う
部屋を使っている人が期日までに家賃を支払わなかったり、部屋を損傷したのに修理費を支払わないなどの場合には、家主は、連帯保証人に支払いを請求する権利を持っています。つまり連帯保証人は、法律的に、あなたに変わって、あなたの債務支払いの義務を負うことになります。
多くの日本人学生の場合には、学費を負担する親族(普通は父親)が連帯保証人になっています。不動産屋や家主は、借りている学生が家賃を払わないときには親に連絡すれば支払ってもらえる、と考えています。
■あなたをよく知らない人は、連帯保証人を引き受けにくい
連帯保証人は債務を伴う保証人ですから、あなたをよく知らない人に「お願いします」といっても、なかなか引き受けてくれないでしょう。あなたをよく知っている人、例えば日本語学校の先生や大学入学時の身元保証人や連絡人などに、まずお願いしてみて下さい。